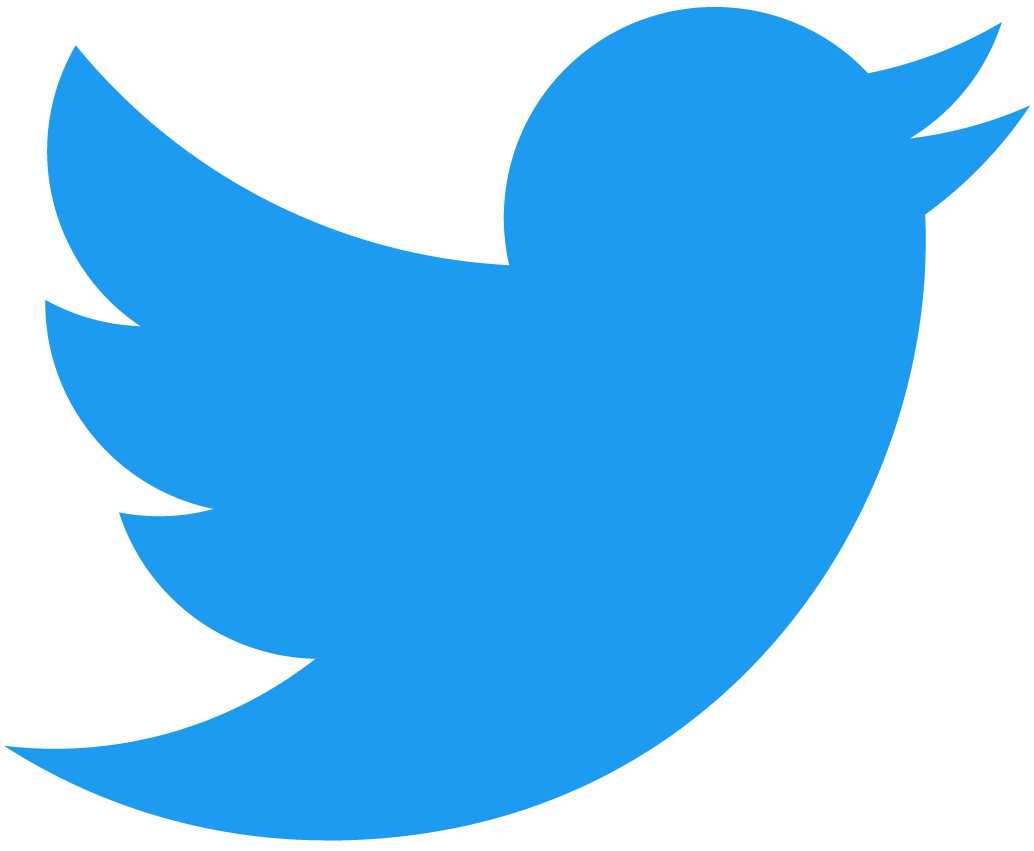ことばの疑問
法律用語はどうして普通の日本語と違ってわかりにくいのですか
質問
法律用語はどうして普通の日本語と違ってわかりにくいのですか。
回答
まず、これらの法律用語をご覧下さい。
- 牽連犯(けんれんはん)
- 善意
- 要件事実
- 瑕疵(かし)
- 審尋
みなさんはこの中で意味をきちんと説明できる用語、あるいは日常的に使っている用語はありますか。
「善意」は知っているし日常的に使うけれども、あとは新聞などで見かけることはあっても意味をきちんと説明は出来ないし、日常的に使うことはない、という人がほとんどでしょう。しかしみなさんが知っている、日常的に使っている「善意」は、実は法律用語として使われる「善意」とは意味が全く異なるのです。
一般的な意味での「善意」は「よい心、親切な心」という意味ですが、法律用語の「善意」は「ある事実を知らないこと」という全く異なる意味になります。「善意」の対義語である「悪意」も同様です。一般的な意味の「悪意」は「悪い心、人に害を加えようとする気持ち」ですが、法律用語では「ある事実を知っていること」という意味になります。このように同じ語であるのに、日常的に使われる時の意味と法律用語で使われる時の意味が異なるものがあるのです。

上記に挙げたその他の語についても意味を挙げると、「牽連犯」は「犯罪の手段や結果が、別の罪名にも触れる場合のこと」、「要件事実」は「一定の法律効果が認められるために必要な具体的事実」、「瑕疵」は「法律上、通常あるべき品質を欠いていること」、「審尋」は「裁判所が、当事者及びその他利害関係者に自由な方式での陳述の機会を与えること」です。どれも専門的な内容で、用語からその意味を伺い知るのが難しいものばかりです。
現在使われている法律用語の基盤は明治時代に遡ります。明治時代は文化、学術等、様々な文物が西洋からやってきました。その際、それらの概念を日本語として受け入れるために、当時の人々は漢語を使って翻訳をするという方法をとりました。法律についても同様です。日本は近代西洋の法典(特にフランスやドイツ)の翻訳を通して、近代的な法体系を作りあげていきました。その際に漢語を多用したことが、法律用語がわかりにくくなってしまった原因の一つです。漢語は漢字を組み合わせることで、新しい言葉を容易に生み出すことが出来る反面、言葉が難解になってしまい、専門外の人にはわかりにくいという欠点があります。また、もともと外国語だったものを日本語に翻訳したことで、混乱を招いたり、日本語として無理があったりする言葉も生まれました。先ほど例に挙げた「善意」「悪意」は原語を翻訳することによって、法律用語と日常のことばとの間で意味に大きな隔たりが生まれてしまった例です。法律用語が難しいのには、以上に挙げたように法律用語の成り立ちが少なからず影響を与えている面があります。
近年では、 裁判員制度により、一般の人も裁判に関わるようになってきたことから、これまでの法律用語を見直し、より日常の言葉に近づけようという動きも出てきています。法律用語を取り巻く社会状況の変化には今後とも注目していくべきでしょう。
参考文献・おすすめ本・サイト
- 林修三(1958)『法令用語の常識』日本評論社
- 林大、碧海純一 編(1981)『法と日本語』有斐閣
- 後藤昭監修、日本弁護士連合会裁判員制度実施本部法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム(編)(2008)『裁判員時代の法廷用語 法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書』三省堂
- 大河内眞美(2009)『裁判おもしろことば学』大修館書店
- 橋内武、堀田秀吾(編・著)(2012)『法と言語 法言語学へのいざない』くろしお出版