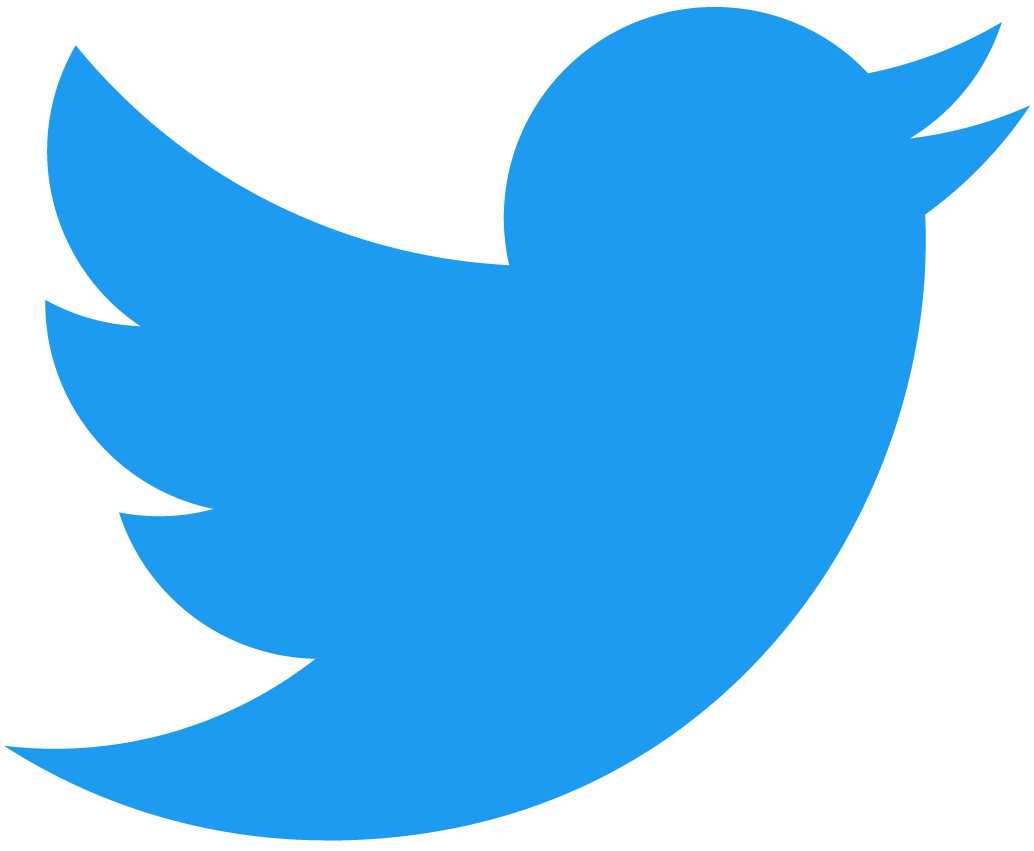ことばの疑問
日本以外に日本語が通じる国や地域はありますか
質問
日本語が通じる人のいる国に旅行に行きたいです。日本以外に日本語が通じる国や地域はありますか。

回答
日本で生まれ育った人は「日本語は日本国内でだけ通用する」と思いがちですが、歴史的な経緯で日本語が広まった国や地域は意外とたくさんあるのでご紹介しましょう。
19世紀末から1960年代前半にかけて、日本人は今とは違う形で海外進出をしていました。当時の日本人は、世界各地に日本語を広めています。
ひとつの流れは、東アジアや太平洋地域への大日本帝国の拡大です。台湾、朝鮮半島、サハリン(樺太)、ミクロネシア(南洋群島)、中国東北部(満州)など、各地に日本人が移り住み、日本語で統治をおこないました。太平洋戦争の敗戦とともにほとんどの日本人は引き揚げましたが、戦前に日本の教育を受けた現地の人たちを中心に、その後も一部で日本語が残っています。
もうひとつの流れは、ハワイや南北アメリカ大陸への移民です。農場労働者として移住した日本人は各地で日系社会を築きました。特に南米移民は1960年代前半まで盛んに続いたので、今も元気な1世の方がいますし、2世以下の日系人はそれ以上に大勢いて、日本語を使い続けています。写真はブラジル・サンパウロの東洋人街リベルダージ地区で、日本語の通じるお店もたくさんあります。

そんな世界各地の日本語の例を見てみましょう。次のうち、台湾・サハリン・ミクロネシアの例は現地の人が使い続けている日本語、ハワイ・カナダ・ブラジルの例は1世や2世以下の日系人の日本語です(用例の出典は記事末尾の引用文献として示します。[ ]で示した現地語の日本語訳は筆者によります)。
(1)guan [私] のa-ma [祖母] 、お嫁あ、○○(地名)にお嫁行った。〔台湾〕
(2)Много [たくさん] も、いっぱい行ぐ人いるって。〔サハリン〕
(3)あの姉さん来たらわかるべさ。〔サハリン〕
(4)何か知らんけどね、家のおじちゃんとてもね、あの、pick up language [ことばを習う] ね。〔ミクロネシア〕
(5)ミー [私] のボーイ [息子] はのお、今ジャッパン [日本] に行っとる。〔ハワイ〕
(6)サタデー [土曜日] はたいていおるけどなー。〔カナダ〕
(7)安いトマテ [トマト] で高いマキナ [機械] 買わにゃならん。〔ブラジル〕
これらの例からわかるとおり、海外の日本語には、(a)現地のことば(台湾語(注)、ロシア語、英語、ポルトガル語など)が混じる、(b)日本各地の方言(西日本方言の「知らん」「行っとる」「買わにゃならん」、東北方言の「わかるべさ」など)が混じる、といった特徴があります。写真はブラジルで開かれたイベントのもので、沖縄のことばが使われています。

筆者はブラジル日系人の方とお話しする機会があるのですが、たまに「私たちの日本語は、ポルトガル語や方言が混ざって、正しい日本語ではないからね」と言われます。謙遜のおつもりかもしれませんが、ポルトガル語や方言が混ざるからこそブラジルの日本語は尊いのだと私は思います。日本各地から移住した人たちが、互いに汗をかきながらブラジルの地に生活を築きあげたことがことばの面にあらわれているからです。日本国内で安穏と育った自分には想像もつかない生活の汗を、その日本語のなかに感じます。
ときどき思うのですが、21世紀の日本社会より、20世紀の日本のほうが、ずっとグローバルな展開をしていたのかもしれません。日系人の方々は、グローバル化の大先輩です。
時代の流れとともに、こうした海外の日本語の話し手は少なくなっています。ですが、世界各地で移民問題に注目が集まり、文化摩擦や言語の壁の問題が取り沙汰される現在、海外の日本語のありかたは、そういった問題に何らかの考えるヒントをくれそうです。
筆者は、海外の日本語のありかたに、今後も多くのことを学び続けてゆきたいと思っています。
(注)台湾には多くの民族が暮らしていますが、多数を占めるのは、17世紀以降に中国福建省から移住してきた人々です。彼らの言語は福建省で話される「閩南語」と基本的に同じもので「台湾語」とも呼ばれます。「閩南語」という言語の名前は知らない人も多いと思い、ここでは「台湾語」と呼びました。
参考文献・おすすめ本・サイト
参考文献
- 渋谷勝己、簡月真(2013)『旅するニホンゴ 異言語との出会いが変えたもの』岩波書店
用例の出典
- 台湾 : 簡月真(2011)『台湾に渡った日本語の現在―リンガフランカとしての姿―』明治書院
- サハリン : 朝日祥之(2012)『サハリンに残された日本語樺太方言』明治書院
- ミクロネシア : ダニエル・ロング、新井正人(2012)『マリアナ諸島に残存する日本語―その中間言語的特徴―』明治書院
- ハワイ : 比嘉正範(1976)「日本語と日本人社会」『岩波講座日本語1 日本語と国語学』岩波書店
- カナダ : 彦坂佳宣(1996)「バンクーバー周辺日系人の言語状況 ―日本語継承の諸相から―」木村一信、奥村剋三(編)『文化の変容と再生』法律文化社
- ブラジル : 長尾勇(1977)「ブラジル日系人の日本語―母国語の忘却と日本語の教育」『言語生活』308 pp.52-60 筑摩書房