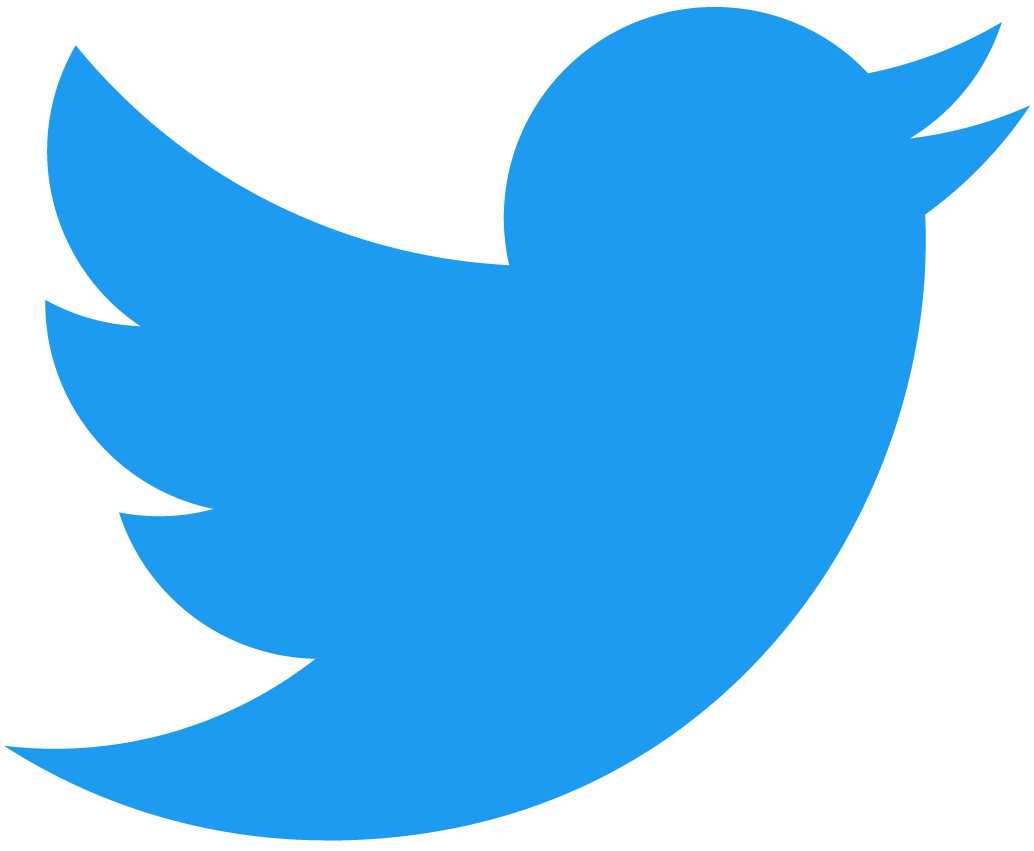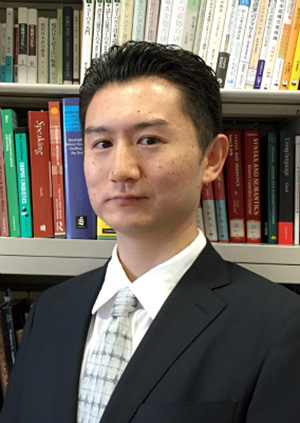ことばの疑問
「シミュレーション」が「シュミレーション」と発音されるのはなぜでしょうか
質問
「シミュレーション」が「シュミレーション」と発音されるのはなぜでしょうか。

回答
英語の綴りは simulation ですから、正しいのは「シミュレーション」です。しかし、日常生活の中では、「シュミレーション」という発音や表記に接することも少なくありません。このような音の変化は、なぜ起こるのでしょうか。音の変化には、他にどのような種類があるのでしょうか。例を挙げながら見ていきましょう。
話し言葉の中では、ある言語表現が本来とは異なる形で発音される場合があります。それが単なる一時的な発音誤りではなく、多くの人によって繰り返し使用される形である場合、それらは「発音のゆれ」と考えられます。「ゆれ」とは、ある一つの言語表現が複数の実現形式を持ち、それらが併存している状態を指します。
『日本語話し言葉コーパス』の中で観察された例を、以下に挙げてみます。本来とは異なる形で発音されている語を、カタカナで示します。
- その場にいた人ゼーインに電話をして
- 大学のジギョーが終わってから
- (まー)ユイツ気に入らないっていうのが
- 家庭のセンタッキで洗うのには
- 言葉以外のコミニュケーションにも慣れて
これらの語は、それぞれ「ゼンイン(全員)」「ジュギョー(授業)」「ユイイツ(唯一)」「センタクキ(洗濯機)」「コミュニケーション」という発音が本来だと考えられます。ところが、発話者が発声を規則的に怠けたり、一定の環境において音の変化が体系的に生じたりすることによって、上記のような「発音のゆれ」が生じるわけです。
では、1.から5.のような発音は、実際にどれくらい現れているのでしょうか。『日本語話し言葉コーパス』の「コア」と呼ばれる、約45時間、50万語分のデータを検索すると、表1のような結果が得られました。

本来とは異なる発音がこれだけの割合で現れている以上、これらは単なる一時的な発音誤りではなく、異なる実現形式が併存している「発音のゆれ」と考えてよいでしょう。
さて、音の変化の種類や特徴に注目すると、上記の例は以下のように分類することができます。
- 撥音(「ン」)が長音(「ー」)になる場合。
類例 : 「店員」→「テーイン」、「原因」→「ゲーイン」など。 - 拗音(特に「ュ」)が脱落する場合。
類例 : 「出張」→「シッチョー」、「手術」→「シジツ」など。 - 連続する同じ母音が単音化する場合。
類例 : 「体育」→「タイク」、「第一」→「ダイチ」 - k や s などの子音(無声子音)に挟まれた母音が脱落する場合。
類例 : 「満足感」→「マンゾッカン」、「大仏さん」→「ダイブッサン」 - 前後の音が入れ替わる場合。
類例 : 「雰囲気」→「フインキ」、「フェミニズム」→「フェニミズム」
この他にも、ワ行が長音化する場合(「柔らかい」→「ヤーラカイ」、「行われている」→「オコナーレテイル」)、外来語の清音と濁音が入れ替わる場合(「バドミントン」→「バトミントン」、「人間ドック」→「人間ドッグ」)など、音の変化にはいろいろなパターンがあります。
さて、表題にある「シミュレーション」→「シュミレーション」の問題は、「5. 前後の音が入れ替わる場合」に該当します。前後の音が入れ替わるこの現象は、「音位転換(metathesis)」と呼ばれます。特にこの場合は、別に存在する「趣味(シュミ)」という語の発音に引きずられて、「シュミレーション」と発音してしまったのかもしれません。このようなケースは「類音牽引」と呼ばれます。「日本道路公団」を「日本ロード公団」と言ってしまうような場合も、これに当たります。
音位転換は、基本的には言い誤りの一種ですが、誤りだったはずのものが正しい形と見なされるようになる場合もあります。例えば、「新しい」と「新たな」は、前者が「アタラ」、後者が「アラタ」で、音位転換が起きた例です。元々は「アラタし」だった語が、平安時代に起きた音位転換で「アタラし」と変化し、それが定着した後、現在に至ります。
また、子どもの言葉の中にも、音位転換がしばしば観察されます。「握手」→「アシュク」、「作る」→「クツル」、「柔らかい」→「ヤラワカイ」、「楽譜」→「ガフク」などは、私の娘が2歳のころに頻繁に発していた音位転換の例です。また、私の小学校時代の恩師によると、6年生の歴史の授業中、私は「藤原鎌足」を「藤原のカタマリ」と何度も言っていたそうです。
参考文献・おすすめ本・サイト
- 北原保雄 編(2004)『問題な日本語』大修館書店
- 寺尾康(2002)『言い間違いはどうして起こる?』岩波書店