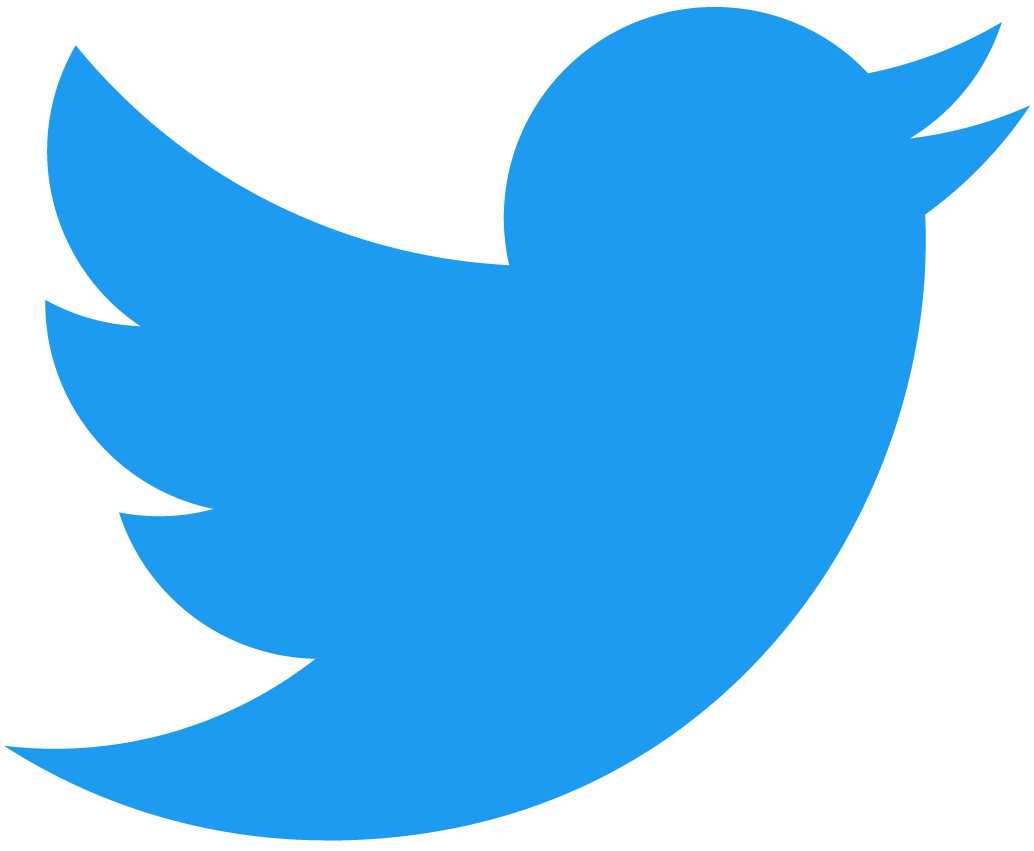ことばの疑問
日本に敬語を使わない地域があるって本当ですか
質問
引っ越した先の人たちは、目上の人に話をするときに敬語を使いません。敬語を使わない地域というのがあるのでしょうか。
※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』18号(2005、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。

回答
敬語の地域差
敬語には、地域によって違いがあります。例えば、目上の人に対し、「(あなたが)書くか」と丁寧に尋ねる場合、共通語では「書かれますか」のように言うでしょう。この場合、「書かれ」の「れ」は、「れる・られる」に基づき、動作の主体に対する敬意を表す尊敬語です。「ます」は、話し相手に対する丁寧な態度を表す丁寧語です。尊敬語、丁寧語ともに多様な地域差が認められます。
尊敬語のない方言、丁寧語のない方言
尊敬語・丁寧語の地域差の一つとして、尊敬語や丁寧語を持たない方言の存在が知られています。
『方言文法全国地図』第6集(参考文献①)には、次の質問文に対して得られた回答に基づく地図が収められています。
「この土地の目上の人に向かって、非常に丁寧に「ひと月に何通手紙を書きますか」と言うとき、「書きますか」のところをどのように言いますか。」
この場面での共通語の言い方は、上記の「書かれますか」などが一般的です。

図1 は、この回答から「書かれます」にあたる部分に尊敬語が現れない地域を抽出した分布図です。これで見ると、尊敬語がなく丁寧語のみ(凡例の書キマス~書クス)の地域は、東日本に広く見られ、西日本では近畿南部から四国を経て九州の東部に連続します。一方、尊敬語も丁寧語もない(凡例の書クの)地域は、東北に分散しつつ、中部にまとまり、紀伊半島南部や九州東部にも見られます。

ところで、〈尊敬語=「れる・られる」相当部分〉、〈丁寧語=「ます」相当部分〉というのは、共通語の文法を当てはめた考え方です。図1 は、「書かれますか」の「書かれます」に注目した地図でしたが、同じ回答における問い掛けの終助詞「か」の分布を示す図2 を見てみましょう。丁寧な場面で使われる問い掛けの終助詞です。図1 で尊敬語も丁寧語もなかった(書クの)地域に重なるように方言特有の形が現れていることが分かります。例えば、三重にはカノシ![]() 、大分には(カ)アンタ
、大分には(カ)アンタ![]() が見られます。これらの地域では、このような終助詞により、「ます」に相当する丁寧さを表現することが報告されています(参考文献②③)。つまり、丁寧さを「ます」に当たる要素で表すというのはあくまでも共通語の文法であって、同じことが、どこの方言にも広く当てはまるものではないことが分かります。
が見られます。これらの地域では、このような終助詞により、「ます」に相当する丁寧さを表現することが報告されています(参考文献②③)。つまり、丁寧さを「ます」に当たる要素で表すというのはあくまでも共通語の文法であって、同じことが、どこの方言にも広く当てはまるものではないことが分かります。

敬語の違いを越えて
敬語の有無や在り方は、それぞれの方言固有の文法に支えられるもので、そこには地域差が存在します。敬語は日本語にのみ存在するものではなく、日本語以外の言語であっても日本語とは別の方法で敬意や丁寧さを表すことが知られています。同じように、方言における敬語は、共通語と必ずしも平行するわけではないのです。それぞれの地域の人々はそれぞれの方言の文法の中で言葉を使っています。共通語を基にすると敬語とは考えにくい別の表現方法で丁寧さが表されていることもあるわけです。そのようなことを理解することが、方言による敬語の違いを乗り越えた伝え合いのかぎになります。
なお、方言による敬語の違いについては、新「ことば」シリーズ12の問22、同17の問10でも取り上げています。合わせて御参照ください。
(大西拓一郎)
参考文献・おすすめ本・サイト
- 国立国語研究所 (2005) 『方言文法全国地図』第6集 国立印刷局 (参考文献①)
- 丹羽一彌 (2000) 『三重県のことば』 明治書院 (参考文献②)
- 糸井寛一 (1983) 「大分県の方言」 『講座方言学9 九州地方の方言』 国書刊行会 (参考文献③)
- 国立国語研究所 「方言文法全国地図」(https://www2.ninjal.ac.jp/past-publications/publication/catalogue/gaj_map/)
※ 地図画像、各巻の解説、参考資料へのリンクをまとめて掲載しています - 国立国語研究所 「方言文法全国地図PDF版ダウンロード」(https://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-pdf/gaj-pdf_index.html)
こちらもおすすめ
- 国語研教授が語る「濁る音の謎」 (1) 鼻濁音 (国語研ムービー)
- 講演「方言の生まれるところ」(第12回NINJALフォーラム) (国語研ムービー)
- 著書紹介 : ことばの地理学 ―方言はなぜそこにあるのか― (ことばの波止場vol.1)
- 漢字にも方言のような地域による違いがありますか(笹原宏之・ことばの疑問)
- 既にお店に入っているのに「いらっしゃいませ」と言うのはなぜですか(居關友里子・ことばの疑問)