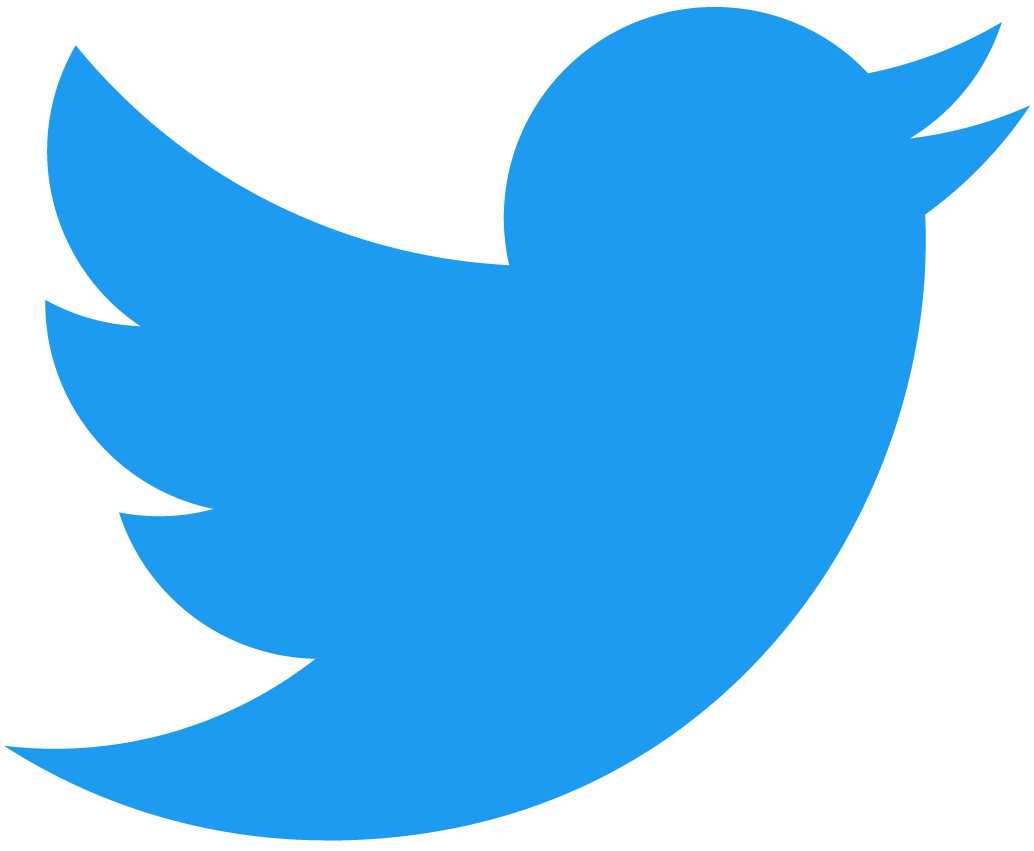ことばの疑問
tsunamiのように、日本語がそのまま外国で使われている例を教えてください
質問
2004年暮れに発生したインド洋大津波のニュースで、英語などでも「ツナミ」という日本語がそのまま使われていることを知りました。同じような例はほかにどんなものがあるのでしょうか。
※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』19号(2006、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。

回答
江戸時代までの場合
他の言語から日本語に取り入れられた「外来語」とは逆に、「ツナミ」のように日本語から他の言語に取り入れられた語のことを、「外行語」と呼びます。ここでは英語の場合を見ていきましょう。大規模な辞典として知られる『オックスフォード英語辞典』第2版(1989年)には、378の日本語が収められています。それぞれの項目には西洋文献での実例が挙がっており、その最も古いものがいつの時代かを見ていきます。もちろん、西洋文献に初めて見られたその時点で外行語になったとは言い切れないわけで、一つの目安ということになります。
まず江戸時代まで(~1868年)では、adzuki(小豆)・bonze(坊主)・hara-kiri(腹切り)・inro(印籠)・katana(刀)・kaki(柿)・kiri(桐)・koi(鯉)・matsu(松)・matsuri(祭り)・miso(味噌)・mousmee(娘)・sake(酒)・samurai(侍)・sen(銭)・shoyu(醤油)・tatami(畳)・urushi(漆)・yashiki(屋敷)・yukata(浴衣)といった語が見られます。いずれも西洋人から見て、珍しくて興味を引かれるような事物や現象に関するものです。このうち最も古い実例はbonzeで、あのフランシスコ・ザビエルの1552年の書簡から引用されています(以上参考文献①②)。

明治・大正・昭和前期の場合
明治・大正・昭和前期(~1945年)になると、日本と西洋との交流が進むのに伴い多くの語が西洋文献で使われるようになります。geisha(芸者)・hanami(花見)・janken(じゃんけん)・judo(柔道)・kabuki(歌舞伎)・kendo(剣道)・ki-mon(鬼門)・maiko(舞妓)・miai(見合い)・nakodo(仲人)・nori(海苔)・onsen(温泉)・romaji(ローマ字)・sensei(先生)・sushi(寿司)・tsukemono(漬物)・udon(うどん)・zaibatsu(財閥)などです。
tsunami(津波)もこの時期で、1897年の文献に初めて見られます。しかし、この語が英語に定着するきっかけとなったのは、1946年4月にハワイを大津波が襲って日系人の多く住む地域も大きな被害を受け、その時彼らの使っていたtsunamiという語が当地の新聞に登場したことだったといいます。この語はロシア語など他の言語でも使われています(以上参考文献①③)。

昭和後期の場合
昭和後期(1945年~)になると、kogai(公害)・itai-itai(イタイイタイ病)・zaikai(財界)・zengakuren(全学連)などの時事用語が見られます。一方、もっと早い時期に見られていてもよさそうな語としては、kokeshi(こけし)・ryokan(旅館)・sumotori(相撲取り)などがあります。時期を問わず目立つ料理関係の語では、shabu-shabu(しゃぶしゃぶ)・teppan-yaki(鉄板焼き)・yakitori(焼き鳥)などがあります。
このほか、karateは名詞「空手」に加え、「空手を使う」という意味の動詞としても用いられています。また興味深いのはshokku(ショック)です。これはshockという英語が日本語に外来語として定着し、それが英語に逆輸入されたということになります。ただこのshokkuは、「ニクソンショック」「オイルショック」のような政治・経済に関する事件に限って使われます。英語ではshockはこういう使われ方はしないようで、両者の間には使い分けがあることになります(以上参考文献①)。

なお、この辞典には出ていませんが、日本の現代文化を象徴する語としてmanga(マンガ)やotaku(オタク)も、今では英語に取り入れられています。
(新野直哉)
参考文献・おすすめ本・サイト
- 福田陸太郎 監修、東京成徳英語研究会 編・著 (2004)『OEDの日本語378』 論創社 (参考文献①)
- 石綿敏雄 (2005)「江戸時代までの外行語」『国文学解釈と鑑賞』70巻1号 至文堂 (参考文献②)
- 加藤秀俊、熊倉功夫 編 (1999)『外国語になった日本語の事典』 岩波書店 (参考文献③)
こちらもおすすめ
- 職業発見プログラム: 明星学園中学、富山県立富山高等学校、宮城県宮城野高等学校
- カナダでfutonと呼ばれるものを見て驚きました。英語のfutonは何を指しますか(平山真奈美・ことばの疑問)
- 明治時代には、漢文のように英語を訓読していたというのは本当ですか(八木下孝雄・ことばの疑問)
- 中国語にとりいれられた日本語(国語研の窓)