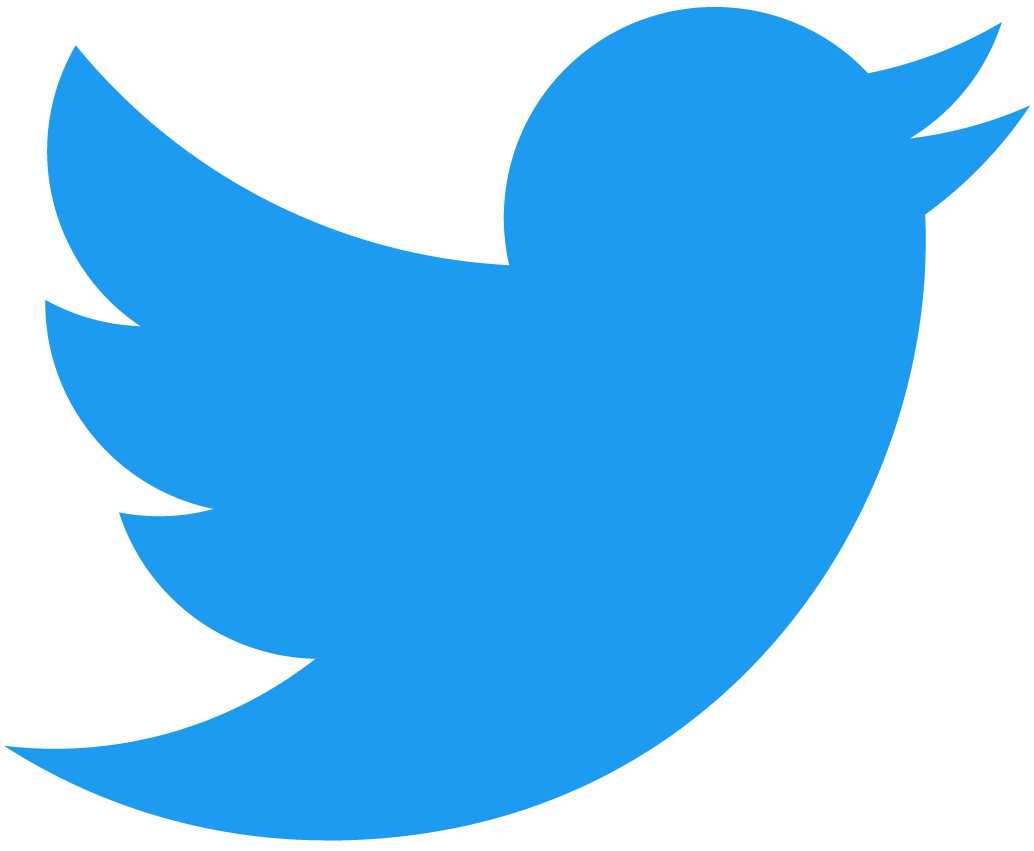ことばの疑問
「スイート・ルーム」の「スイート」は〈甘い〉という意味ではないのでしょうか
質問
ホテルの「スイート・ルーム」の「スイート」というのは〈甘い〉という意味で、新婚旅行でよく使われるからそう言うのだと思っていましたが、先日英語に詳しい友人から「それは間違いだ」と言われました。本当なのでしょうか。
※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』14号(2001、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。
※ 2024.2.27 一部記載を修正しました。
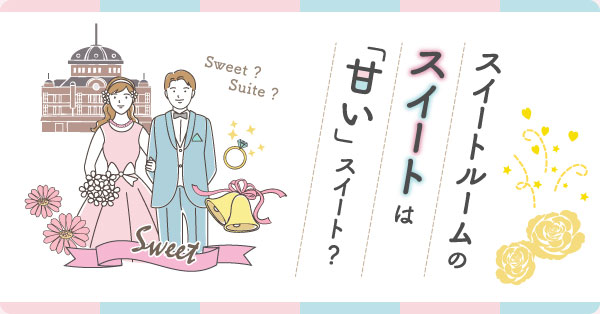
回答
同じ「スイート」でも……
それはその友人の言うとおり間違いです。日本語で言う「スイート・ルーム」は本来の英語では「スイート」だけで表し、sweet ではなく suite とつづります。この suite とは、寝室と居間など、二つ以上の部屋がひとまとまりになっているタイプの客室を指します。これが sweet と解釈されてしまう背景には、外来語として使われる「スイート」は「スイート・ポテト」「スイート・コーン」「スイート・ホーム」など sweet〈甘い〉である場合が多いこと、さらに質問文にもあるとおり新婚旅行などでカップルがよく泊まることが考えられます(なお sweet と suite は英語でも発音は同じです)。

このようにある語の語源を本来の語源とは違うように解釈してしまうことを、言語学では「民間語源(説)」「語源俗解」などと呼びます。子供のころによくある、「カレーライス」は「辛えライス」なのだと思ったり、「すき焼き」はみんなが「好き」だからそう言うのだと思ったりする(本来「すき」は農具の鋤で、この上で調理をしたことからこの名前がついたと言われています)のも、その一種です。
しかし中には、大人も含めて大多数の人が語源を本来のものとは違うように考えている語もあります。
「ムショ」は「ケイムショ」?
刑事もののドラマや映画などで、「あいつはムショ帰りだ」「ムショに三年行った」といったセリフがよく使われます。この「ムショ」の語源は何か、調べてみましょう。
こう言われたら、「そんなの『ケイムショ(刑務所)』の略に決まってるじゃないか」と思う人が多いのではないでしょうか。しかし『日本国語大辞典』初版(小学館)には次のようにあります。
- むしょ
- 【虫・六四】[名](「むしよせば(虫寄場)」の略「むしよ」の変化した語)監獄のことをいう。盗人仲間の隠語。「むしょ帰り」〔隠語集覧〕 補注 「刑務所」の略と解されることもあるが、「監獄」を「刑務所」と改称したのは大正一一年(一九二二)で、この語はそれ以前から使われていた。
ここに見られる『隠語集覧』という本は大正4(1915)年に京都府警察部が発行したものですが、そこには確かに
- むしょ
- 監獄―類語「むしよせば」ノ略
とあります。「ムショ」は本来は「刑務所」の略ではなかったのです。
しかし今のような「民間語源」はかなり早くからあったようで、昭和10(1935)年に警察協会大阪支部が発行した『隠語構成様式並に其語集』の「むしよ」の項には、次のようにあります。
- 刑務所。「むしよせば」の略にして、刑務所の省略に非ず刑務所のことを「むしよ」といへるはずつと以前から生ぜり「むしよ」を刑務所の省略と誤信する者は、非常な誤りである
なお『隠語集覧』『隠語構成様式並に其語集』ともに、「むしよせば」は「六四寄せ場」であり、監獄の食事の飯は麦と米が六対四の割合であることから来ているとしています。
語源を考えるためには
このように、「ムショ」の語源が「刑務所」ではないことは明らかです。ただ、今から80年以上前に刊行された『隠語集覧』に載っている隠語は、「ホシ」(容疑者)や「デカ」(刑事。この語は、当時の私服巡査が角袖の和服を着ていたことから「かくそで」→「でかくそ」→「でか」という過程を経て生まれたと言われています)など少数を除けば我々にはなじみのないものです。その中で「ムショ」が現在に至るまで使われ続けてきた背景には、これを「刑務所」という一般に知られた名称の略語だと考える語源意識があったことも確かです。
「スイート・ルーム」が〈甘い・部屋〉でないことも、「ムショ」が「刑務所」の略でないことも、大型の国語辞典をいくつか調べればわかります。語源というものを考えるにあたっては、たとえ「これが語源だろう」とすぐ思いつくような語であっても、とりあえず辞典を、できれば語源辞典や隠語辞典のような特殊な辞典を引いてみる、という態度が必要だと言えます。
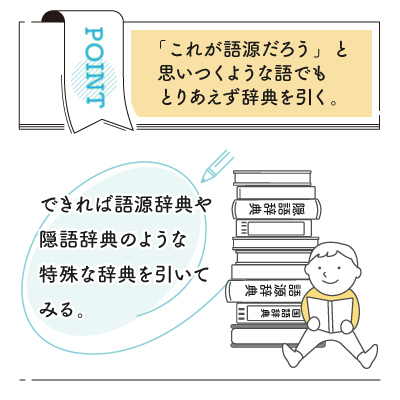
参考文献・おすすめ本・サイト
- 隠語辞典集成 2『隠語集覧』(1996) 大空社
- 隠語辞典集成 8『隠語構成様式並に其語集』(1996) 大空社
- 木村義之、小出美河子(編)(2000)『隠語大辞典』 皓星社
- 前田富祺(監修)(2005)『日本語源大辞典』 小学館
- 米川明彦(編)(2020)『 日本俗語大辞典 新装版』 東京堂出版
こちらもおすすめ
- tsunamiのように、日本語がそのまま外国で使われている例を教えてください (新野直哉・ことばの疑問)
- 今年はイヌ年ですが、なぜ「犬年」でなく「戌年」と書くのですか (片山久留美・ことばの疑問)
- 「シュークリーム」は“和製外来語”か (山田貞雄・ことばの疑問)
- 「コンセント」の語源・由来 (山田貞雄・ことばの疑問)
- 著書紹介 : 近現代日本語の「誤用」と言語規範意識の研究 (橋本行洋・ことばの波止場)
- 暮らしに生きることば「ニックネームの由来」 (新野直哉・国語研の窓)
- ことばQ&A「「役不足」とは?」 (新野直哉・国語研の窓)
- コラム「全然、納得いってます」 (新野直哉・国語研の窓)